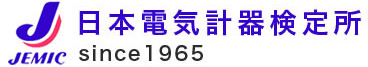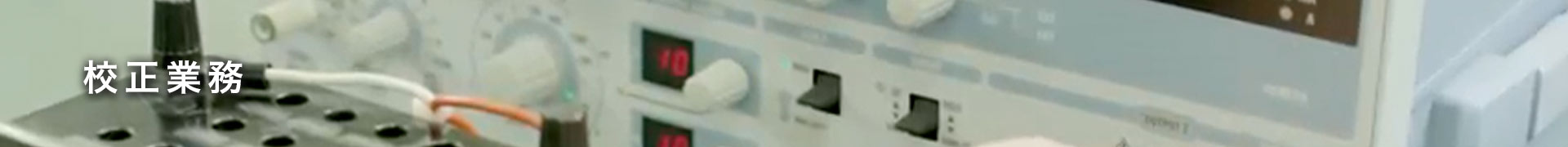
- 日本電気計器検定所TOP
- 校正業務
- 校正サービスのご案内
- テクニカルコラム
- 「圧力とは」
「圧力とは」
圧力は、私たちの生活の中であまり意識されることはありませんが、実は便利なツールとして様々な場面で活用されています。例えば、身近なものでは、自動車や自転車のタイヤに必要な「空気圧調整」、天気予報の台風の強さなどを表す「気圧」、蒸気の力を利用して調理する「圧力鍋」、上水道の「水圧」や血液が血管にかける圧力を示す「血圧」などがあげられます。このように、定量化された圧力はさまざまな分野で活用されています。
圧力の単位には、Pa(パスカル)が使われています。この名称は、圧力に関する基本的な法則「パスカルの原理」を発見したことで知られる人物ブレーズ・パスカル(Blaise Pascal)に由来しています。ただし、圧力の単位は用途によっていくつか使い分けられており、例えば、血圧ではmmHg(水銀柱ミリメートル)、地球の標準的な大気圧を表す単位としてはatm(アトム)が使われることもあります。また、一部の技術分野ではMKS単位系によるkgf/cm2 (重量キログラム毎平方センチメートル)なども使用されています。このように、圧力の単位は分野ごとに様々ですが、国際単位系(SI単位)では、固有の名称と記号を持つ22個のSI組立単位の1つとしてPa(パスカル)が正式な単位として採用されています。気象の分野で使用されているhPa(ヘクトパスカル)が、日本においては1992年12月1日にミリバールからヘクトパスカルに置き換えられたことで、記憶に残っている方も多いと思います。
圧力とは、「単位面積に作用する力の大きさ」と、国際単位系(SI)で定義されています。その基本単位である1 Pa(パスカル)は、1 m2(平方メートル)の面積に対して1 N (ニュートン)の力がかかっている状態を表します。
関係式で示すと1 Pa = 1 N/m2(ニュートン毎平方メートル)となります。
圧力の表し方にはいくつかの種類(ゲージ圧、差圧、絶対圧)があり、基準の違いによって区別されます。
まず、ゲージ圧は「大気圧」を基準とした圧力で、それより高ければ「正圧」、低ければ「負圧」と呼ばれます。これら両方を測ることができるものは、特に連成計と呼ばれることもあります。
次に、差圧は、任意の基準圧力(ライン圧力)に対してどれだけ差があるかを示すもので、配管内の圧力差などを測る際に使われます。
そして、絶対圧は「完全真空」を基準とした圧力です。完全真空とは、物質や力が一切存在しない状態のことで、圧力ゼロの基準点といえます。たとえば、標準大気圧の1 atmは、絶対圧で101.325 kPaになります。
こうした圧力を測定するのが圧力計です。圧力計にはいろいろな種類があり、デジタル表示のものをはじめ、機械的に指針を動かすブルドン管圧力計や隔膜(ダイヤフラム)式圧力計、物体のたわみ量を電気信号として出力する圧力センサや圧力変換器(トランスデューサ)などがあります。それぞれに特長があり、用途や測定対象に応じて使い分けられています。これらの圧力計は、水道やガス、工業プラント、自動車など、幅広い分野で使われています。
JEMICでは、圧力計のゲージ圧力(気体圧力、液体圧力)および差圧(気体圧力)について校正を実施しておりますので、圧力計の校正をご検討される際は、是非一度、お問い合わせください。
(2025.9 A)
計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について