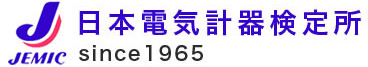情報箱
テクニカルノート
JEMICが発行しているサークルニュースから、技術情報を掲載しているページを御紹介します。
計測関係用語集
計測に関わる用語の中から、特に頻繁に使用される用語の定義を集めました(JIS Z 8103から転載させていただきました)。
計測
特定の目的をもって、測定の方法及び手段を考究し、実施し、その結果を用いて所期の目的を達成させること。
(JIS Z 8103から一部転載)
計量
公的に取り決めた測定標準を基礎とする測定。
(JIS Z 8103から一部転載)
測定(measurement)
ある量をそれと同じ種類の量の測定単位と比較して、その量の値を実験的に得るプロセス。
注記1:測定は、測定結果の利用目的にかなう量の記述、測定手順、その手順に従って動作する校正された測定システムの存在が前提となる。
注記2:一般に、測定で得られる結果は単一の値ではなく、注記1に記載した前提の下でその量に合理的に結び付けることが可能な値全ての集合と
考える。
注記3:ある量と測定単位との比較は、間接測定においては、その量に関連する他の種類の量の測定を通じて間接的に行われる。
注記4:事物の計数は次元1の量の測定単位との比較であり、測定の一種とみなされる。
注記5:測定は、名義的性質には適用されない。
(JIS Z 8103から一部転載)
校正(calibration)
指定の条件下において、第一段階で、測定標準によって提供される不確かさを伴う量の値とそれに対応する指示値との不確かさを伴う関係を確立し、第二段階で、この情報を用いて指示値から測定結果を得るための関係を確立する操作。
注記1:校正は、表明(statement)、校正関数、校正線図、校正曲線又は校正表の形で表すことがある。場合によっては、不確かさを伴う、指示
値の加算又は乗算の補正で構成することがある。
注記2:校正は、“自己校正(self-calibration)”と呼ばれる測定システムの調整(adjustment)、又は校正の検証(verification)と混同すべきで
はない。
注記3:上記の定義の第一段階だけで校正と認識していることがある。
(JIS Z 8103から転載)
トレーサビリティ(traceability、metrological traceability)
個々の校正が不確かさに寄与する、切れ目なく連鎖した、文書化された校正を通して、測定結果を参照基準に関係付けることができる測定結果の性質。
注記1:この定義では、“参照基準”は、現示された測定単位の定義、順序尺度量でない量の測定単位を含む測定手順、又は測定標準のいずれとも
なり得る。
注記2:トレーサビリティには、確立された校正階層が必要である。
注記3:参照基準の詳述には、校正階層を確立する際にこの参照基準を用いた時期のほかに、校正階層の中で最初の校正をいつ行ったかなど、参
照基準に関連する他の計測情報を含める。
注記4:測定モデルで入力量が複数ある測定の場合、各入力量の値はそれ自体がトレーサビリティをもつことが望ましく、関係する校正階層は分
岐構造又はネットワークを形成していることがある。各入力量の値のトレーサビリティを確立するために必要となる作業は、測定結果に
対する相対的寄与に釣り合ったものであることが望ましい。
注記5:測定結果のトレーサビリティは、不確かさが与えられた目的に対して十分であること、又は誤りがないことを保証するものではない。
注記6:二つの測定標準の比較が、一方の測定標準の量の値及びその不確かさを確認し、必要であれば補正するために行われる場合には、その比
較を校正とみなすことがある。
注記7: “トレーサビリティ”という用語は、“測定のトレーサビリティ”の意味で用いられる以外に、“試料のトレーサビリティ”、“文書のトレーサ
ビリティ”、“機器のトレーサビリティ”、又は“物質のトレーサビリティ”といった他の概念で用いられることがあり、これらの場合には、
あるアイテムの“履歴(trace)”が明確であるという意味をもたせている。したがって、それらと混同する可能性があると思われる場合に
は、“測定のトレーサビリティ”、又は“計量計測トレーサビリティ”、“計測トレーサビリティ”、若しくは“計量トレーサビリティ”のいずれ
かを用いることが望ましい。
(JIS Z 8103から転載)
測定標準、エタロン(measurement standard、etalon)
何らかの参照基準として用いる、表記された量の値及びその不確かさをもつ、ある与えられた量の定義を現示したもの。
注記1: “量の定義の現示”は、測定システム、実量器又は標準物質によって与えることができる。
注記2:測定標準は、他の同種の量に対して測定値及び不確かさを確定し、それによって、他の測定標準、測定器又は測定システムの校正を通し
て、トレーサビリティを確立する際の参照基準としてしばしば用いられる。
注記3:“現示(realization)”という用語は、ここでは最も一般的な意味で用いている。これは“現示”の三つの手順を示している。第一の手順は、
測定単位の定義からの物理的実現であり、“厳密な意味(sensu stricto)”での現示である。第二の手順は、測定単位の定義からの現示で
はなく、物理現象に基づいた再現性の高い測定標準を組み立てることで、例えば、長さ(メートル)の測定標準を確立するための周波数
安定化レーザ、電圧(ボルト)確立のためのジョセフソン効果、又は電気抵抗(オーム)確立のための量子ホール効果の使用などの場合
にみられる。これは“再現(reproduction)”と呼ばれている。第三の手順は、実量器を測定標準として採用することで、例えば、1 kg測
定標準の場合がある。
注記4:測定標準に付随する標準不確かさは、常に、その測定標準を用いて得られる測定結果での合成標準不確かさ(ISO/IEC Guide 98-3:2008の
2.3.4参照)の一成分である。この成分は、合成標準不確かさの他の成分と比べると小さいことが多い。
注記5:量の値及び不確かさは、測定標準を用いた時点で決定する。
注記6:同じ又は異なる種類の幾つかの量を、一般に測定標準とも呼ばれる一つの装置で実現することもある。
注記7:科学技術分野では、英語の用語“標準(standard)”は少なくとも二つの異なる意味をもつ。一つは記述、技術的勧告又は類似の規範文書
(仏語では“norme”)という意味であり、もう一方は測定標準(仏語では“étalon”)というものである。
注記8:測定標準を指す用語としては、基本単位の値そのものを現示したものを指す“原器(prototype)”、計器及び実量器を指す“標準器”なども
使用される。
注記9:計量法では、法定計量分野で特定計量器の検定又は定期検査に用いる測定標準を“基準器”と呼んでいる。
注記10: “測定標準”という用語は、他の計測ツール、例えば、“ソフトウェア測定標準”を意味するために用いることがある(ISO 5436-2参照)。
(JIS Z 8103から一部転載)
測定値(measured value、measured quantity value)
測定結果を表す量の値。
注記1:測定の反復による複数の指示値がある場合、個々の指示値を、対応する個々の測定値を求めるために用いることができる。また、この
個々の測定値の集合を、平均又は中央値のような測定の代表値を計算するために用いることができる。このような代表値は、通常、個々
の測定値よりも付随する不確かさは小さい。
注記2:測定対象量を表すと考えられる真値の範囲が不確かさと比べて小さいときは、測定値は本質的に一意的な真値の推定値であると考えるこ
とができ、反復測定によって得られた個々の測定値の平均又は中央値を測定値とすることが多い。
注記3:測定対象量を表すと考えられる真値の範囲が不確かさと比べて小さくないときは、真値の集合の平均又は中央値の推定値を測定値とする
ことが多い。
注記4:ISO/IEC Guide 98-3:2008では、“測定の結果”及び“測定対象量の値の推定値”(単に“測定対象量の推定値”ということもある。)という用
語を、“測定値”の意味で用いている。
(JIS Z 8103から転載)
真値、真の値(true value、true quantity value)
量の定義と整合する量の値。
注記1:測定の解釈における誤差アプローチ(error approach)では、真値が一意的で、実際には知ることのできないものと考えられている。不
確かさアプローチ(uncertainty approach)では、量は本来どこまでも詳細に定義できないため、単一の真値は存在せず、量の定義と整
合する複数の値からなる真値の組が存在すると考えられている。ただし、この真値の組は、原理的にも実際にも知ることはできない。そ
れ以外の評価手法では、真値の概念は不要であるとして、測定の妥当性評価において測定結果の両立性の概念を適用している。
注記2:基礎定数という特殊な場合、その量は単一の真値をもつとみなされている。
注記3:測定対象量に付随する、定義による不確かさが、不確かさの他の成分と比べて無視できるほど小さいと考えられるときは、測定対象量は
“本質的に唯一の”真値をもつと考えることができる。これは、ISO/IEC Guide 98-3:2008及び関連文書が採用している評価方法であり、こ
の場合、“真の”という修飾語は冗長と考えられている。
(JIS Z 8103から転載)
取決めによる(量の)値(conventional value)
ある与えられた目的のために、合意によって、量に付与された値。
注記1:この概念を意味するものとして“取決めによる真値”という用語を用いることがある。ただし、その用語を用いることは推奨しない。
注記2:取決めによる量の値は、真値の推定値であることがある。
注記3:取決めによる量の値は、一般的には十分に小さな(ゼロの場合もある。)不確かさを伴うものとして受け入れられている。
(JIS Z 8103から一部転載)
(測定)誤差(measurement error、error)
測定値から真値を引いた値。
注記1:この定義は、ISO/IEC Guide 98-3:2008及びJIS Z 8103:2000を含む多くの計測関係の文献で採用されている。
注記2:ISO/IEC Guide 99:2007は、“測定値から量の参照値を引いたもの”と定義している。ISO/IEC Guide 99:2007の定義に従えば、“測定誤差”の
概念は、次の場合に用いることができるとしている。
a) 引用する量の参照値が一つだけある場合:このような状況が生じるのは、不確かさが無視できる測定値を用いて測定標準によって校正
を行う場合、又は取決めによる量の値が示されている場合である。この場合、測定誤差は既知である。
b) 測定対象量が一意的な真値、又は無視できるほど狭い範囲に存在する真値の集合で表すことができると考えられる場合:この場合、測
定誤差は不可知である。
注記3:測定誤差と、生産工程の誤差又は過失とを混同すべきではない。
(JIS Z 8103から転載)
真度、正確さ(trueness、measurement trueness)
無限回の反復測定によって得られる測定値の平均と参照値との一致の度合い。
注記1:“真度”は測定値のかたよりの小ささを表す概念であり、数値で表現することはできないが、一致の度合いの尺度はJIS Z 8402規格群に規定
されている。
注記2:真度は系統誤差とは逆の関係となるが、偶然誤差には関係しない。
注記3:“精確さ(measurement accuracy)”という用語は、“真度(measurement trueness)”の意味で用いるべきではない。また、用語“真度”
の代わりに用語“正確さ”を用いる場合、用語“精確さ”と同じ発音であることに留意する。
注記4:JIS Z 8101規格群では、“measurement accuracy”を“(測定の)精確さ”、“measurement trueness”を“(測定の)真度”、
“measurement precision”を“(測定の)精度”という。
注記5:測定器について“推定したかたよりの限界の値で表した値”を“正確度”ということがある。
(JIS Z 8103から一部転載)
精密さ、精度(precision、measurement precision)
指定された条件の下で、同じ又は類似の対象について、反復測定によって得られる指示値又は測定値の間の一致の度合い。
注記1:“精密さ(measurement precision)”は、通常、指定された測定条件下での標準偏差、分散、変動係数などの、不精密さ(imprecision)
の尺度によって数値表現する。
注記2: “指定された条件”には、例えば、繰返し条件、中間再現条件又は再現条件がある(JIS Z 8402-1:1999参照)。
注記3:精密さは、測定の繰返し性、中間再現性及び再現性を定義するために用いる。
注記4: “精密さ(measurement precision)”は、精確さ(measurement accuracy)を意味するものとして誤って用いられることがある。
注記5:JIS Z 8101規格群では、“measurement accuracy”を“(測定の)精確さ”、“measurement trueness”を“(測定の)真度”、
“measurement precision”を“(測定の)精度”という。
注記6:従来、機械・物理分野では用語“精度”を精確さの意味で使っており、化学分野では用語“精度”を精密さの意味で使ってきた。意味の混同の
おそれがない場合は、“総合精度”又は“精度”を用いることができる。“精度”を用いる場合、“精確さ”と“精密さ”とのどちらの意味で使って
いるかを明確にしておくことが望ましい。
注記7:精密さを推定した数値で表した値を“精密度”ということがある。
(JIS Z 8103から一部転載)
繰返し性、併行精度(repeatability)
一連の測定の繰返し条件の下での測定の精密さ。
(JIS Z 8103から転載)
再現性、再現精度(reproducibility)
測定の再現条件の下での測定の精密さ。
(JIS Z 8103から一部転載)
補正(correction)
推定した系統効果に対する補償。
(JIS Z 8103から一部転載)
不確かさ(uncertainty)
測定値に付随する、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の広がりを特徴づけるパラメータ。
注記1:不確かさは、補正及び測定標準の付与された量の値に付随する成分のような、系統効果から生じる成分及び定義による不確かさを含む。
推定した系統効果を補正せず、代わりにそれに関連する不確かさの成分を含める場合がある。
注記2:パラメータは、例えば、標準不確かさと呼ばれる標準偏差(又はその指定倍量)でも、又は明示された包含確率をもつ区間の幅の半分で
もよい。
注記3:不確かさは、一般に多くの成分からなる。そのうち幾つかの成分は、不確かさのタイプA評価に基づき、一連の測定によって得られる量の
値の統計分布から評価され、標準偏差によって特徴づけることができる。その他の成分は、不確かさのタイプB評価に基づき、経験又はそ
の他の情報に基づく確率密度関数から評価され、これも標準偏差によって特徴づけることができる。
注記4:一般に、ある与えられた一連の情報に対して、不確かさは、報告される測定値に付随すると理解される。異なる測定値を報告する場合、
付随する不確かさも変わる。
注記5:この定義は、ISO/IEC Guide 98-3:2008に基づく。
注記6: “不確かさ”という用語が測定の不確かさを表すか否か明確でない、又はそれを明確にすることが必要な場合、“測定不確かさ”又は“測定の
不確かさ”を用いる。
(JIS Z 8103から転載)
標準不確かさ(standard uncertainty)
標準偏差として表した不確かさ。
(JIS Z 8103から転載)
(不確かさの)タイプA評価(Type A evaluation of uncertainty)
指定された測定条件の下で得られる一連の測定値の統計的解析による、不確かさの一成分の評価。
(JIS Z 8103から一部転載)
(不確かさの)タイプB評価(Type B evaluation of uncertainty)
不確かさのタイプA評価以外の方法による、不確かさの一成分の評価。
(JIS Z 8103から一部転載)
合成標準不確かさ(combined standard uncertainty)
測定モデルの入力量に付随する個々の標準不確かさを用いて得られる標準不確かさ。
(JIS Z 8103から一部転載)
拡張不確かさ(expanded uncertainty)
測定結果について、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の分布の大部分を含むと期待する区間を定める不確かさ。
注記1:“大部分”によって表される割合は、この区間の包含確率又は信頼の水準とみなすことができる。
注記2:拡張不確かさが定める区間に特定の包含確率を結び付けるためには、測定値及びその合成標準不確かさによって特徴づけられる確率分布
に関する明示的又は暗黙の仮定が必要となる。この区間に結び付けられる包含確率は、そのような仮定が正当化できる程度以上の厳密さ
で知ることはできない。
注記3:この定義は、ISO/IEC Guide 98-3:2008に基づく。
(JIS Z 8103から転載)
包含係数(coverage factor)
拡張不確かさを得るために合成標準不確かさに乗じる数として用いる数値係数。
注記1:包含係数は、通常2から3の範囲にある。
注記2:この定義は、ISO/IEC Guide 98-3:2008に基づく。
(JIS Z 8103から転載)
測定器、計測器(measuring instrument)
測定を行うために、単独で、又は1台以上の補助装置と併せて用いる装置。
注記1:単独で使用可能な測定器は、測定システムである。
注記2:測定器は、指示測定器又は実量器である。
注記3:特に機械的運動を用いて測定するものを“測定機”ということがある。
注記4:“測定器”と“計測器”との違いは、“測定”及び“計測”の定義を参照する。
(JIS Z 8103から一部転載)
指示測定器、指示計器(indicating measuring instrument)
測定される量の値に関する情報を伝える出力信号を与える測定器。
注記1:指示測定器には、その指示値の記録を出力するものもある。
注記2:出力信号は、視覚的又は聴覚的に示されることがある。出力信号は、1台以上の別の装置に伝送されることもある。
(JIS Z 8103から一部転載)
表示測定器、表示計器(displaying measuring instrument)
出力信号を視覚的に表示する指示測定器。
(JIS Z 8103から転載)
直線性(linearity)
入力信号と出力信号との間の直線関係からのずれの小さい程度。
(JIS Z 8103から転載)
公称値(nominal value)
測定器又は測定システムを適切に用いるための手引となる、測定器又は測定システムを特徴づける量の丸め値又は近似値。
(JIS Z 8103から一部転載)
器差(instrumental error)
a)指示値から真値を引いた値。
b)標準器の公称値から真値を引いた値。
注記1:一般的に真値の代用として参照値が用いられる。
注記2:正しい値を得るには指示値又は公称値から器差を引けばよい。
(JIS Z 8103から転載)
固有誤差(intrinsic error)
指定された標準状態における測定器又は測定システムの誤差。
(JIS Z 8103から一部転載)
付加誤差(complementary error)
影響量の値が指定された標準状態の値と異なるために生じる測定器又は測定システムの誤差。
(JIS Z 8103から一部転載)
分解能(resolution)
対応する指示値が感知できる変化を生じる、測定される量の最小の変化。
注記:分解能は、例えば、ノイズ(内部又は外部)又は摩擦に依存することがある。さらに、測定される量の値に依存することもある。
(JIS Z 8103から転載)
識別しきい(閾)値、識別限界(discrimination threshold)
対応する指示値に検出可能な変化を生じない、測定される量の値の最大の変化。
注記1:識別しきい(閾)値は、例えば、ノイズ(内部又は外部の)又は摩擦に依存することがある。さらに、測定される量の値、及び変化の
与え方に依存することもある。
注記2:測定される量の値にヒステリシスが存在する場合、識別しきい(閾)値と分解能は異なる値となる。
注記3:値ではなく測定器の能力を示す場合には“識別能”という用語が用いられる。
(JIS Z 8103から転載)
(測定器の)安定性(stability of a measuring instrument)
測定器の特性が時間的に一定であるという測定器の性質。
注記1:安定性は、幾つかの方法で定量化される。
注記2:長期の時間経過に伴って生じる特性の変化を“経年変化”という。
(JIS Z 8103から一部転載)
機器のドリフト(instrumental drift)
測定器の特性の変化による,指示値の連続的又は漸進的な経時的変化。
注記:機器のドリフトは、測定される量の変化にも、認識されたいかなる影響量の変化にも関係しない。
(JIS Z 8103から転載)
許容差(tolerance)
基準にとった値と、それに対して許容される限界の値との差。
注記1:一般に、“公差”は“指定された最大値と最小値との差”の意味で用いられる。
注記2:計量法では、検定公差、基準器公差のように、“許容差”の意味で“公差(対応英語はtolerance)”が用いられている。
注記3:英語の用語“tolerance”は、日本語の用語“許容差”又は“公差”の意味で用いられている。
注記4:“ばらつきが許容される限界の値”の意味で“許容差”が用いられることがあるが、“最大許容誤差”又は“誤差限界(limit of error)”を用いる
ことが望ましい。
注記5:許容差は、基準にとった値に対する比又は百分率で表すこともある。
(JIS Z 8103から転載)
最大許容誤差(maximum permissible error)
既知の参照値に関して、ある与えられた測定、測定器又は測定システムの仕様又は規則によって許されている測定誤差の極限値。
注記1:“最大許容誤差”は、二つの極限値がある場合に用いられる。また、同じ意味で“誤差限界(limit of error)”が用いられている。
注記2:“最大許容誤差(maximum permissible error)”を指すときは、“公差(tolerance)”という用語を用いるべきではない。
注記3:電気分野では、“指定された条件における最大許容誤差で表した測定器の精度”の意味で、“確度”が用いられている。
(JIS Z 8103から転載)