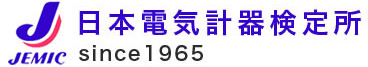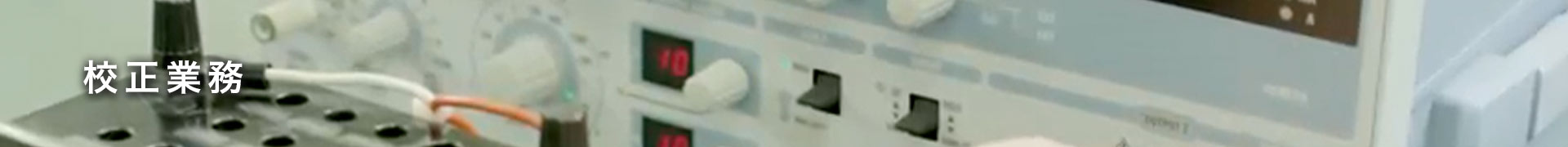
- 日本電気計器検定所TOP
- 校正業務
- 校正サービスのご案内
- テクニカルコラム
- 照度測定時に注意すべきこと
照度測定時に注意すべきこと
照度計の照度値の校正は、標準電球を用いて行いますが、これは、測光標準が標準電球のもつ相対分光分布を利用して組み立てられているためです(この状態のことを、以下、標準測定状態と呼びます)。この校正結果からは、標準測定状態における照度計の固有誤差(系統誤差)を把握することができます。したがって、標準測定状態における照度測定では、照度計の表示値にこの固有誤差を補正することで、より正確な測定結果が得られます。
一方、実際の使用環境では、LED電球の普及等により測定対象の光の特性が標準測定状態とは異なる場合が大半です。このような場合、正しい測定結果を得るには、固有誤差の補正に加え、色補正係数という数値を乗じる必要があります。色補正係数の求め方は文末に記載しておきますが、光源の相対分光分布や照度計の相対分光応答度などを個別に計測及び解析する必要があり容易ではありません。このため、測定の現場では、色補正係数を乗じないケースも少なくありません。つまり、標準測定状態以外の測定においては、固有誤差が補正されていたとしても、色補正係数の影響が残り、最終的な測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。
色補正係数の影響を小さくしたい場合にはどうすればよいのでしょうか。これには、照度計の相対分光応答度が標準分光視感効率関数V(λ)にできるだけ近い特性を持つ機種を選択することが必要です。
ただ、先にも述べましたが、照度計の相対分光応答度を個別に計測することは容易ではないため、その簡便な方法としては、照度計の相対分光応答度と標準分光視感効率関数V(λ)との近似度合いを示す指標である「標準分光視感効率からの外れ」が小さい照度計を選ぶようにします。日本産業規格(JIS C 1609-1:2006)では、この外れの限度を、階級(精密級、AA級、A級)ごとに、それぞれ3 %、6 %、9 %として定めていますので、求める精度により必要な階級を選択します。
AA級及びA級における「標準分光視感効率からの外れ」の限度値を模擬した相対分光応答度を基に、当所の白色LED照明を測定した場合の色補正係数を試算したところ、色補正係数が取り得る値の範囲は、AA級ではおおよそ0.98~1.02及びA級では0.97~1.03程度となりました。
以上より、照度の測定において色補正係数を乗じない場合、その影響量をなるべく抑えるためには、性能が明らかなJIS規格品の使用が有効な対策といえるでしょう。
参考
色補正係数kの求め方
k= ∫λ1λ2 Ss(λ)・s(λ)dλ・∫λ1λ2 st(λ)・V(λ)dλ ∫λ1λ2 Ss(λ)・V(λ)dλ・∫λ1830 st(λ)・s(λ)dλ
ここで
V(λ) :標準分光視感効率関数
St (λ):光源の相対分光分布
Ss (λ):標準光源の相対分光分布
s(λ) :照度計の相対分光応答度
s(λ) :λ1:光の波長の下限(一般に360 nm)
s(λ) :λ2:光の波長の上限(一般に830 nm)
(2025.7 G)
計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について