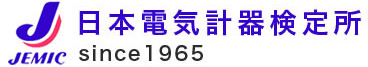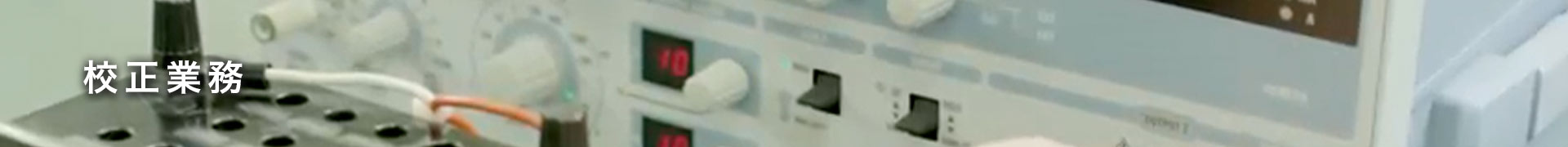
- 日本電気計器検定所TOP
- 校正業務
- 校正サービスのご案内
- テクニカルコラム
- クランプメータについて
クランプメータについて
クランプメータは、測定対象の回路を切断する必要が無く、主に負荷に流れる電流や漏れ電流を測定する場合などに用いられます。機種によっては交流電流測定、直流電流測定に加えて、様々な電流を測定することが可能なタイプもあります。
例えば、漏れ電流を測定する場合は、図に示す測定個所で電流を測定します。漏れ電流とは、電気機器の電源ケーブルの被覆の劣化や、電気機器内部の絶縁不良などによって、電流が本来の電気回路以外の経路(たとえば筐体や接地線)に流れてしまう電流をいいます。通常、漏れ電流が発生していない状態では、電源から負荷に流れる電流I1と負荷から電源に帰る電流I2が等しくなり、図のようにI1とI2両方を挟んで測定すると原理的にはゼロが表示されます(現実的には様々な要因により完全なゼロにはならないことは多々あります)。また、負荷と接地(アース)を接続しているアース線には電流I0は流れません。これらがゼロでない場合は何らかの原因で漏れ電流が発生していることが確認できます。

なお、歪んだ波形の電流を測定する場合、クランプメータにおいても指示計器と同様に電流検出の方式によっては、正確な実効値を測定できない場合があります。このような場合、平均値整流方式(MEAN)ではなく、真の実効値方式(True RMS)のクランプメータを使用する必要があります。また、モーターなどの電気機械では、電源投入時に瞬時的に大きな電流が流れることがあり、これを突入電流といいます。クランプメータのピークホールド機能を利用することで、この突入電流を測定することが可能となります。
クランプメータを使用する場合は、次の事項に注意しましょう。
- ・測定する導体は、クランプメータの電流センサ部(コア部)の中心に位置するようにセットする。
- ・電流センサ部の開閉口の先端がしっかりと閉じていることを確認する。
- ・直流電流を測定する場合は、電流の方向(極性)を正しく合わせ、測定前に必ずゼロ調整を実行する。
電流を検出するセンサとして、ロゴスキーコイルの原理を応用した製品もあります。このようなセンサは、オシロスコープや電力解析装置との組み合わせでクランプメータと同様に、交流電流やパルス電流の波形測定に広く使用されています。ロゴスキーコイルは、センサ部と表示部が一体のクランプメータで多く採用される磁性体にコイルを巻いて電流検出を行う構造とは異なり、空芯コイルで構成されています。実際には、空芯ではなく柔軟な非磁性体の構造材にコイルを均等に巻いて形成する構造がとられることが多いです。
このような構造であることから、磁気コアのあるクランプメータと比較して柔軟性が高く、狭いスペースや密集した配線の電流測定にも適しています。また、ロゴスキーコイルは小さな電流や低周波数域における測定は苦手ですが(直流はそもそも測定できません)、磁気飽和がないので大電流の測定に向いており、雷電流などの瞬間的な非常に大きな電流(インパルス電流)の測定にも使用されています。ロゴスキーコイルを使用して雷電流を測定しているので有名なのが東京スカイツリーであり、風力発電設備の管理でも使用されています。
JEMICにおいては、クランプメータの校正を実施しておりますJCSS校正も可能ですので、校正をご検討される際は、是非一度、お問い合わせください。
(2025.8 S)
計測器の校正業務
校正サービス
デジタル校正証明書等の発行について
デジタル校正証明書等のダウンロードについて
お見積り・お申込みの手続きと、納期・費用について